群馬大学
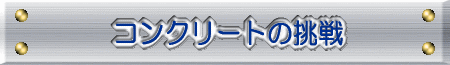
| 群馬大学工学研究科 博士前期課程1年 高見 満 |
| 当研究トップへ | ||
| 1. | はじめに | |
| 2. | 今回のタイトルは何を意図していますか | |
| 3. | コンクリート構造物の耐久性について |
|
| 4. | コンクリート構造物の耐久性向上のために現在取り組んでいる研究 | |
| 4.1 | 電気泳動法の適用 | |
| 4.2 | コンクリートの細孔構造 | |
| 5. | 最後にひとこと | |
| 群馬大学工学部 建設工学科 杉山 隆文 助教授 |
| 3.コンクリート構造物の耐久性について コンクリートを使用することによって、任意の形状・寸法の部材や構造物を造ることができ、しかも材料の入手が比較的容易であり、経済的であることは知られているところです。また、耐久的な材料であり元々、メンテナンスフリーであると信じられてきました。したがって,改造や解体・廃棄などが容易ではない側面はありますが、長持ちするので、あまり心配はされてきませんでした。つまり、一度造ってしまえば、半永久的に存在する材料であると考えられてきた面が少なくないと考えます。実際に、小樽港の防波堤は、100年経った現在でも、北国の過酷な環境条件の下で、立派にその役目を果たしています。 しかし、1980年代に「コンクリート・クライシス」としてNHKの特集でも取り上げられた話題があります。すなわち、コンクリート構造物の塩害や中性化など耐久性へ疑問が投げられました。最近では、1999年6月に発生した山陽新幹線の福岡トンネル内でコンクリート塊が落下した事故が記憶に新しいと思います。このようにコンクリート構造物はメンテナンスフリーなものではないことを認識しなければならない事象が次々と明らかにされつつあります。 このような状況を踏まえて、土木学会コンクリート委員会は、1999年にコンクリート標準示方書[施工編]−耐久性照査型へと改訂し、2001年にはコンクリート標準示方書[維持管理編]を新たに制定しました。これらの示方書は、耐久性のあるコンクリート構造物を構築することや維持管理を通じてコンクリート構造物を長持ちさせる技術的な指針を示しています。[維持管理編]の制定作業や2002年に再度改訂された[施工編]の改訂部会に参画した委員の一人として、これまでのコンクリート構造物の耐久性や維持管理技術に関する最新の知見を反映できたものと考えています。土木工学は、実社会の発展に直結した実学ですので、これまでに行った研究成果やそれに関連した知見が実社会に直接反映されるのはうれしいものです。 |
|