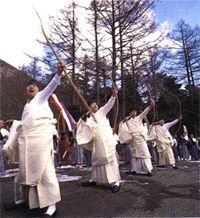|
|
|
|
| 1 |
�_���i���傤�j |
�@�[�����i���Ⴈ���j����������C�̎ւ����ƂȂ�A������l��s�̓������R���������B���Ȃ݂ɁA���̐[�����́u���V�L�v�ɂ��o��A�O���@�t�̊�@���~�����_�Ƃ��Ă��m���Ă���B |

�[������ |
| 2 |
�_�ޏ������i�����������������ǂ������j |
�@��C�푈�Ŋ��R�Q�d�Ƃ��āA�����R���ɗ��Ă����鋌���{�R����������B |
| 3 |
���̋{�i�֗��_�j�i���킳���̂��݁j |
�@������l7�̎��A���Ɍ���ꕧ�̓��ւƓ����������V�q���J���Ă���B |
| 4 |
�V�C��m�������i�Ă������������傤�ǂ������j |
�@�����R�ю�ƂȂ�A�敾���Ă��������R�M�������B����ƍN�ɋC�ɓ����A���E�G���A�O��E�ƌ��ƎO����̓��쏫�R�Ɏd�����B |
| 5 |
�[�������i���Ⴈ���ǂ��j |
�@����120�������͂��݁A�_���̐^�������ɗ������������B������l�̓������R���������[�������J���Ă���B |
| 6 |
���Y���i���낤�����j |
�@����530�N�̘V���B����43���[�g���A�ڒʒ��a5.75���[�g���A���͂̐����̒��ł��Q�������ċ���Ȑ��B���Ȃ݂ɁA�u���Y�v�͌����A���j��D�ꂽ�j�q���Ӗ����A��ԌÂ����̂�ł��傫�Ȃ��̂ȂǂɎg��ꂽ���̂ł�����B |

�����؊�i�肩��{�{�_�Ђւ̐Βi�B�T���H�ւ̓�����B

�{�{�_��

�l�{�����ƎO�d���� |
| 7 |
�����؊�i��
�i�����Ȃ݂�������Ёj |
�@�ƍN�̎���A�Ɛb�F�������j�����Ƌ{�ւ̎Q�������̂��ߓ����X��3�����ɐA������������i�����ۂ̋L�O��B |
| 8 |
�{�{���i�ق������j |
�@�����؊�i��e�̏����ȑ�B���ʂ����Ȃ��A����Ă��Ȃ��Ƃ����B |
| 9 |
�{�{�_���i�ق�����j |
�@767�N�A������l����r�R���j�̎R�̐_���܂��J��ׂɑn�������_�ЂŁA������r�R�_�Ђ̎n�܂�ƂȂ�B���_�����i�����R�։����̊�j�ƕ��сA�����R�̐M�̋N���Ƃ����Ă���B |
| 10 |
�l�{�������_���i���ق��イ���������j |
�@�����̑�J���n����������l��10�l�̒�q���A���������Ǝ��_�̗��������i��ڂɂ��A���̒n�ɍs���Ă݂�ƁA�傫�Ȑ��琴���i���j�A�鐝�i��j�A���Ձi���j�A�����i�k�j�̎l�_���킢���ƌ����B������766�N���̒n�Ɏ����������u���_�����v�i�������イ���A��̎l�{�����j�Ƃ��A�͎��_�Ɩ��t�����B |
| 11 |
�l�{�����O�d���i���ق��イ�����イ�̂Ƃ��j |
�@1219�N�ɈÎE���ꂽ�������̗���Ԃ߂邽�߂ɑ���ꂽ�B���݂̌����́A�����������̂����đւ������́B |
| 12 |
�l�{�����ω����i���ق��イ������̂�ǂ��j |
�@�哯2�N�i807�N�j�A���썑�i�A�k�����i�����ȂƂ��͂�j�ɂ����ω����J��ꂽ�B�l�{�����͂��Ƃ��ƁA�u���_�����v�i�������イ���j�ƌĂ�Ă�������ɉ������ꂽ�B |
| 13 |
���ʓ��i�����܂ǂ��j |
�@���̐́A�O�@��t����C������_�ЂŏC�s���A�召��̌��̋ʂ���ь����̂������A�ǂ��Ă݂�ƁA�������ʂ́A�l�{�����߂��ŏ����A�傫���ʂ͒��T���̕����֔�ы������Ƃ����B
�����̎v�������ƍl����t�͏������ʂ̏������ꏊ�ɂ��������������ʓ��Ɩ����A�傫�ȋʂ̂��߂ɁA���T���߂��ɖ����������������A�ƌ����Ă���B |
| 14 |
�b�ǖL���@�L�����i������Ԃ̂��݂ނ˂Ђ�ǂ������j |
�@���݂̓��Ƌ{�L�����ԏ�A���̔n��������ɂ��铺���ŁA�b�ǖL���@�L�́A�ƌ��ɂ�銰�i�̑呢�ւ̍ۂ̓��Ƌ{�̐v�E�{�s�̐ӔC�҂ō쎖���哏���B |
| 15 |
���ߑm�s�̕��i���傤�т����̂͂��j |
�@�����m�s�́A������l�ƂƂ��ɓ������J����10�l�̒�q�̒��ł���Ԃ̍���ŁA��l�̎���A�Ղ����œ����̍���ƂȂ����B�l��{��l�ւ̒��S���[���A���Ƌ{�����ɍۂ��A���x���m�s�̕���ړ]���悤�Ƃ��������̓x�ɋ��낵�����Ƃ��N������ɂ͒f�O�����Ƃ��������`�����c���Ă���B |
| 16 |
�{���@���i�悤���Ɓj |
�@�ƍN�̑����A���Z�̕��̕�F�����ߎo�̉p���@�ɂ��1626�N�Ɍ��Ă�ꂽ�B�����m�Ԃ����̍ד��s�r�̓r���œ�����K�ꂽ�ہA���Ƌ{����ɗ���������Ƃ���Ă���B�����ȍ~�͔p���ƂȂ�A���݂͕�ƍ��Ղ̂ݎc��B |
| 17 |
�J�R���i��������ǂ��j |
�@������l���J��ׂɌ��Ă�ꂽ��h��̓��B�����ɂ͖{���n����F���Ə�����l�̍����A����ɂ͒�q10�l�̖ؑ����[�߂��Ă���B |

�J�R���ƎY�̋{

�f�R���̘Z���V�� |
| 18 |
������l�̕��i���傤�ǂ����傤�ɂ�̂͂��j |
�@817�N������l���S���Ȃ����ہA����J��䶔��i�Α��j�ɂӂ���A�����͒J�̏���ɖ������ꂽ���A���Ƌ{�����ɂ��킹�A��l���J��ׂɊJ�R�����������ꂽ�B���݂͂����ɖ�������Ă���B��l�̕�̉��ɂ́A��q3�l�̕�����Ă��A�������l�Ɏd���Ă���B |
| 19 |
�ω����i�Y�̋{�j |
�@�J�R���̍����Ɍ��Ă�ꂽ�A�k���ω��i�悤��イ����̂�j���J�鏬���ȎЂŕʖ��u���ԓ��i���傤����ǂ��j�v�Ƃ��Ă�Ă���B���̖��͈��Y�F�肩��R�����Ă���A�܂������ɂ̂ݐi�ގ��̂ł��鏫���̋�u���ԁv�̂悤�ɁA�܂������Ɍ��C�Ȏq�������܂��悤�ɂƂ̊肢���������Ă���B
�@���ԓ��ɕ�[���ꂽ���Ԃ�1�����A�薳���Ɏq�������܂ꂽ��A�肽���Ԃ̋�ƁA����傫����Ƃ����ɓ��ɕԂ��Ƃ������킵������A���ɂ͌��݂ł���R�̋����ł���B |
| 20 |
�A�z���i����悤�����j |
�@�ω�������ɂ���2�̎��R�ŁA���Y�F�肩��A���ꂼ��j�Ə���\���Ă���B |
| 21 |
����ƘZ���V���i�قƂ�����E�낭�ԂĂ��j |
�@�J�R���̗��̐藧�����f�R�ŕ��Ɏ����₪����ł������Ƃ���u����J�v�ƌĂ�Ă������A�n�k�ŕ���Ă��܂����B���݂́A�Z���V�̐Ε������u���J���Ă���B |
| 22 |
�k��_��
�i�����̂���j |
�@�_�ЂƂ����������Ȃ��A�u�~����v�̂��鋐�Ɛ��̐���ł��Ă���B�w��Ə����̐_�E�������^���J�����_�ЂŊw�����Ə����̏�B���F�肵�Ă̎Q�q�҂������K�ꂽ�B |

�k��_�Ђ̔~�����������

�����������̑� |
| 23 |
��|���i���������j |
�@�w��Ə����̐_�Ƃ��Đ��߂�ꂽ�k�̐_�Ђ��w�ł���A���̐��u��Ō����āv�����A��_�I�ɏ���Ɗw�₪���シ��ƌ����Ă���B���݂́u����|���ā��悹�āv�F��Ɨǂ��Ƃ���Ă���B |
| 24 |
�_�n�̔��i����߂̂Ёj |
�@�ւ����̐킢�̍ہA�ƍN������������n�ׂ̈Ɍ��Ă�ꂽ��B�ƍN���̎���14���1630�N�Ɏ��B |
| 25 |
�ѐ����E�������i�������肷���E���傤�����j |
�@�����R��44���ʓ��ƂȂ�������������_�Еt�߂ɐA���������{�Ƃ������鐙�Q�Łu�������v�ƌĂꂽ�B���̂����̈�{�͂܂�ł������Ɣт�グ���悤�ɖ���ɖڗ��������߁u�ѐ����v�ƌĂꈤ���ꂽ���A1963�N�A�˕��œ|��Ă��܂����݂͌����Ȃ��B |
| 26 |
�召�����̔��i�������傤�����̂Ёj |
�@�s�ғ��E����_�ЁE�ω����ւ̂x����H�ɗ����W�ŁA����ȍ~�A����_�Ђւ̕����͐��n�ƂȂ�̂ő召�ւȂǂ̕s������Ă͂Ȃ�ʂƂ̒m�点���A�Q�q�ɖK��銿���̓ǂ߂Ȃ��l�ɂ��ǂ߂�悤�ɂЂ炪�ȂŋL���Ă���B |
| 27 |
�����m���i���炢�Ƃ̂����j |
�@�O�@��t�̑���_�Бn���ɂƂ��Ȃ��A���n�Ƃ��āA�C�s�̏�Ƃ��ĉh�����B�̂͑�ڂɂđ�t���C�s�����Ƃ̌����`�������邪�A���݂͑�ڂ͂Ȃ��A������10���قǂ̗��₩�ȗ��ꂪ�����邾���B�l�G��ʂ��Ĕ������A������ɖK���ό��q�͌��݂������B |
| 28 |
�ʏ����i�ׂ����傠�Ɓj |
�@����_�Ђ̕ʓ����������Ƃ����ꏊ�B�����R�։����ɓ`���_���u���ю��i�����͂��j�v�̎n�܂�̒n�ƌ����Ă���B |
| 29 |
�e�����i�悤���������j |
�@�u�e���v�Ƃ͐_�������̎p�ł��̐��Ɍ����邱�Ƃ������B���̐́A�O�@��t�����̋��̑O�Ő_��̍~�����F�肵���Ƃ���A���������_�����ꂽ�Ƃ����B |
| 30 |
�^�����̒����i���߂��̂Ƃ肢�j |
�@�����m��e�̐Βi��o��ƌ����Ă��钹���B�����̐ΔŁE�z�тɊJ�����ۂ����ɁA�R�̏��𓊂��A���܂�����ʂ�K�^�������~���ƌ����Ă���B���݂��A�����̕t�߂ɂ͎Q�q�҂̓����������U����Ă���B |

�^�����̒����ɐ𓊂���ό��q

����_�� |
| 31 |
����_���i�����̂�����j |
�@820�N�^���@�c�A�O�@��t����C�����R�����ۂɑn�����ꂽ�Ƃ����B1617�N�ɓ��Ƌ{�����������܂ŁA�����̎R�x�M�̒��S�Ƃ��Ă����Ƃ��l�C�̍����_�Ђ������B |
| 32 |
�����т̍��i����ނ��т̂����j |
�@����_�Ћ������ɂ���B�e�w�Ə��w�������g���č��̗t��ꂸ�Ɍ��Ԃ��Ƃ��ł���Ηlj��ɏ��荇���A�܂��́A���l���m���Е����̎�̐e�w�Ə��w���g�����܂����ׂ�Η��H�����܂��䂭�Ȃǂ̏���������A�lj������߂Ă̎Q�q�����������Ƃ����B���݂͍����͂�Ă��܂��̂�h�����ߍ������Ԃ��Ƃ͋ւ����Ă���B��Јꎛ�A���E��Y�̐_�Е��t�ŋ��߂����݂������̕��@�Ō��Ԃ̂��ǂ��B |
| 33 |
���O���i�ނ˂���j |
�@���̐́A���E�Ƃ̋��Ƃ��đ����Ɏ��]���M�̐��E�ɐg�𓊂���҂̓n�鋴�Ƃ��āu���O���v�ƌĂ�Ă������A�����炩�A����R�M���猒�r�F��̂��߂́u�肢���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�Z�����̐����A�����̔N��̕����i20��20���j�œn��Ə���R�R���̉��̋{�܂œo���������ƂƓ����ƂȂ�肢�����Ȃ��ƌ����Ă���B |
| 34 |
��_�E�O�{���i������ڂ��E����ڂ��j |
�@�O�@��t�����̒n�ŏC�s���Ă����ہA�c�S�P�������ꂽ�ꏊ�Ƃ���Ă���B����̌�_�̎O�{���͖�300�N�O�ɓ|�ꌻ�ݗ����Ă���͓̂��ځB����7�N�i1667�N�j�A�{���@�R�w�̉��l�̏��m����_�����āu�Ȃ�Ə�������_���v�Ɣn���ɂ����r�[�A�_���ɂ���Č��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����B |
| 35 |
�����א_���i�����̂����Ȃ肶��j |
�@�O�m11�N�i820�N�j����_�ЂƂƂ��ɍO�@��t�ɂ���đn�����ꂽ�B���̐́A��t�����̂�����������������Y��Ă��܂��ƁA��ׂ̐_���܂������Č���ꂨ���������Ñ������Ƃ����B |
| 36 |
���̐��i�����̂����݁j |
�@�̂��炱�̐�̐��Ŏ������ƂƂĂ��㎿�Ȏ����ł���ƐM�����Ă��āA�������Ǝ҂̐M�������B�������Ĉ��ނƎ��̖�������Ƃ����B |

����R�o�R��������Ɍ��Ă�ꂽ�s�ғ��B�T���H�͂�������Βi�̉��蓹����Q�@������܂ő����B |
| 37 |
�q����i�����˂����j |
�@�j�ՒT���H�F����R�[�X�̍ł����A����������J��ꂽ�ŁA���̐Ɋ肢��������Ǝq��Ɍb�܂��ƐM�����Ă���B���݂ł��q����������悤�ɂƊ�|���ɖK���l�������Ƃ����B |
| 38 |
�s�ғ��i���傤����ǂ��j |
�@�ޗǎ���̎R�x��p�ҁA���̏��p�i����̂����ʁj���J�铰�Ŗ��̏��p�����r�ł��������Ƃ���A����R�̓o�R���Ɍ��Ă�ꂽ���̓��ɂ́A���r�ɂȂ�悤�ɂƍs�҂����܂�������ƌ����Ă���B�܂����̎ア�҂͂����ɎQ�q����Ƒ�����v�ɂȂ�Ƃ̌��`�������葽���̐M�҂��K�ꂽ�B���݂̓��͕���2�N�ɉ������ꂽ���́B |
| 39 |
���|�n���i�����������j |
�@���̐́A�n�������j�̎R�ւ̓��R�����Ƃ����ꏊ�ɂ���A�O�㏫�R�F����ƌ��̒��b�A�����L��璉�H�̕�����Ă�ہA�������Ɉ����Ƃɂ���đ������ꂽ�B�Ȃ��A���̒n���̔w��ɂ������Q�@�ƌ��_�����A�ƌ��̕�̑O��ɂ́A�������N�Ɏd����Ƃ��āA�������H�Ɠ��������b�F����ǂ̕悪���Ă��A�ƌ��̕������Ă���B |