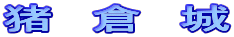
いのくらじょう
もっとくわしく
-
どこにあるの?
観音山(かんのんやま)のいただきにあります。泉福寺のうら側の山だよ。登山口が二つあるけど、硯石(すずりいし)の方とはちがうから気をつけて登ってみてね。
-
何か残ってるの?
雷神様(らいじんさま)のほこらを中心に幅が約3.5mで土が低く盛り上げてあるんだよ。
-
どんな役わりをしていたの?
この場所から南西に「小倉城・板橋城」があり、その備えとして見はりの役わりをしていたと考えられているよ。
- いつごろたてられたの
この城をたてた人ははっきりわからず二つの説があるよ。
- 正応年間(1288〜1293)に鹿沼権三郎入道教阿説(かぬまごんざぶろうにゅうどう・・・?)がたてた,
- 大永年間(1521〜1528)に鹿沼教清(かぬまのりきよ?)のけらい鹿沼右衛門(かぬまうえもん?)が鹿沼城の支城(しじょう)として建てた。
というせつだよ。
(人物の名前はくわしい読み方がわからないんだ。もし知っている人がいたらおしえてね。)
- だれのお城だったの?
鹿沼右衛門という人で、あとで神山下総守(かみやましもうさのかみ)と名のって鹿沼城のお殿さま壬生綱雄(みぶつなお?)の家来になったそうです。天正4年にこのひとの弟(壬生徳雪斎)と仲間になって、綱雄をあんさつしました。ところがこの綱雄の息子の義雄(よしお)という人にぎゃくに責められ徳雪斎は自殺、右衛門は板橋近棟に殺されてしまったのです。
- いつごろなくなっちゃったの?
板橋親棟(いたばし ちかむね?:板橋城の城主)という武将にせめられ猪倉城は落城(らくじょう:負けて城がとられてしまうこと)しました。城のあとつぎがいなくなったため、廃城(はいじょう:しろをなくすこと)したとのことです。1523年(大永3年)と伝えられているよ。
このあたりの話は犬塚のページも読んでね。
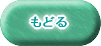

この説は渡辺武雄氏の著書「故里百話 今市の懐旧」に載せられているもを著者の了解をとって小学生向けにやさしく書きなおしたものです。
![]()