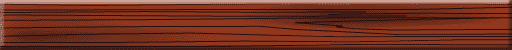
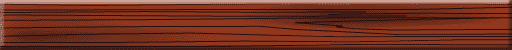
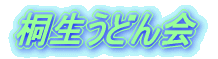
平成10年9月29日に26事業所で発会
桐生市が日本で最初に通産省からファションタウン(FT)に指定され商工会議所にFT推進運営委員会ができその中に活性化委員会ができ、その一委員に私がいました、私の職業は飲食業で、私の人生の使命は食を通じて世の中に貢献することです。
そこで、桐生地区を、どうしたら食で活性化できないか、考えました。
商工会議所の会員名簿で飲食業で一番多い業態はなにか、調べました、ダントツに多かつたのが、うどん屋でした。
数の多い業態で活性化することが、桐生地区の活性化には一番効果があると考えたからです。
なぜ、桐生うどん会の会長をしてるのか? うどん屋でもないのに。
この運動を通じて桐生地区が全国の人々から、うどんの美味しい町と一度、認知していただくことができれば、未来永劫、うどんを食べにきてくれます、名物として通販でも売れるようになるでしょう、この運動は、今、桐生に生きている人々だけの、ものではなく、子供や孫、100年先の桐生の人々の為とおもつています。
運動半ばですが、順調に推移していると思っています、うどん会のメンバーの方々のご努力、商工会議所はじめ応援してくれている多くの方々のお陰です。手前みそですが当社(サンフード、グルメフーズ)の社員の皆様、事務局やったり、イベントのときは休み返上で手伝ていただいています。地域に貢献するという経営理念を実践してくれています。
又、麺の食文化をもつた町が隣あつて、まとまつた地区は日本中に無い、大変めずらしい所と、かねがねおもつていましたので、そのことを、両毛5市の関係者の皆さんに話したところ、皆さんも同じように思ってたようで、すぐに話がまとまり、今年の4月13日に「麺の里」両毛5市の会が発会しました。
桐生うどん会を盛り上げながら、「麺の里」両毛5市の会の活動もしていこうとしています、車の両輪で両方すすめることが、桐生うどん会にとっても良いことと考えています。
桐生うどん会のキャチフレーズは「西の讃岐に東の桐生」と日本中の人々に言ってもらえるようになろうです、桐生には歴史的にも「うどんの里」としての充分な要素を持っています。
1、うどん屋さんの数が日本一。
人口1万当りのうどん屋の数が、高松市の倍ちかくあります。。なぜ桐生にこれほどのうどん屋があるのか不思議でしたが、桐生 は日本の機(はた)どころ、機を織つてたのは女性です、今と違い、昔は機屋(織物工場)は残業があたりまえでした、私の家も 機屋でしたので毎日が残業でした。その当時はそうゆうものだと思っていました又桐生には大きいうどん屋は少なく、小さなうどん屋が辻辻にあります、機織りの女性が手が離せなかったので、手軽に食べられるうどんを出前でとるという習慣ができとおもわれます。
2、室町時代からつづいていた庚申さまの日には朝までうどんを食べるという習慣があつた。
10年くらい前まで梅田石鴨地区ではその習慣があつたそうです。
3、桐生のうどんは都(みやこ)うどん。
1200年前に白滝姫が桐生に織物を伝えたと言われていますが、その時にうどんも一緒に伝えられたのではないかとおもわれます、 京都に行き、ビックリしたのは、京都もうどん処ですが、代表的なお店(市役所で権兵衛、権太、おめん、など10店ほど紹介 してもらう)を回ったところ、麺せん、 食感、うすくち醤油の店が多かったけれど、桐生とまつたく同じ汁の店もありました。織物 の町は昔から京都とつながりが深いので、うどんの盛んな町が多いそうです。そんな関係で桐生のうどんはおしゃれなのだと思 います。
4、冠婚葬祭にはうどんがつく。
今でもお葬式にはうどんとおはぎがつきますが、昔は結婚式にもうどんがついたそうです。この習慣は全国的なものとおもつてま したがこの地区独特なのだそうです。
5、お客様をもてなす一番の方法は、うどんをぶっておむかえすること。
最近は私自身そういうことを経験してませんが、昔、何度かありました。
6、この地区は昔は毛の国といわれていました。
上毛、両毛、今でも上毛新聞、両毛線など名前がのこってますが、毛とは小麦のことだそうです、この地区は昔から小麦の国だ つたようです。
7、桐生はうどんとそばの比が8:2
先日、県が音頭をとつて館林と桐生をうどんで全国に売りだす為にはどうしたら、いいかということを調査、研究してくれました。
東洋大学の先生が調べてビックリしてました。ちなみに館林は5:5でした。この数字も日本一かもしれません。
8、桐生ほど手打ちうどんにこだわつた地区はない。
桐生では手打ちうどんが当たり前ですが、他の地区では手打ち保存会など作り、手打ちの技術をのこそうとしている。
この地区は小規模の店がほとんどなので手打ちで十分だつたのではないか、もう一つ大きな理由は桐生のうどん屋は何々系( 川野屋、藤屋、山本、宮島、など)といわれる店が多いので、のれん分けで伝統を重んじる風土をもつていた。
まだ、他にもあると思いますが、うどん会を始めてから教えていただいたことです。
戦後は代用食としてうどんが食べられたので、いい印象をもつてない人もいるようですが、その前の時代はうどんはご馳走だったと考えられます、庚申さま、冠婚葬祭、もてなし方法、などでわかります。
今後の桐生うどん会の進め方
1、なんといっても美味しいうどんにこだわりつづけること、
たしかに、桐生のうどんは美味しいけれど、日本のうどん処にする為には、今のレベルではダメだと思つています。
2、マーケティングができてない。
2年前にうどん会で名古屋に研修にいき、参加してくれたメンバーは、皆さん感じました。
若者がラーメン屋ではなく、うどん屋でカレーうどん、や、みそ煮込みうどんを食べている光景を見て、若い人にも受け入れられ るメニューを開発しなければと強くおもいました。
3, 麺類商組合でうちだしたカレーうどん
この運動は素晴しい、うどんの町で町興ししてる所は多いけれど、日本にカレーうどんの町はない。日本のオンリーワンになれ る。又カレーうどんは、客層を若者からお年寄りまで、貧しい人からお金持ちまで、幅広くとれる。
桐生のうどん屋にはほとんどの店でやつており、一番商品として売りだしている店も多い
桐生には群馬大学があり、有名な芭蕉さんのカレーは、昔、インドの留学生におそわつたということを聞いたことがあります。
そのながれで桐生のうどん屋さんにはカレーうどんがあるのではないかと思われます。
4、同じような店ばかり
切り口の違う、個性的な店も必要
5、ひもかわうどん
桐生の最大の特徴は彼岸から彼岸まで鍋に使われるひもかわうどんだと思います、一部の店では年間とうしてやつてる店もで てきて、大変良い傾向だと思います。ひもかわうどんの生かし方も今後の課題とおもつています。
6、観光用のうどん学校を作りたい
1時間くらいでうどん作りを体験してもらい、打ちたて、ゆでたてを食べていただく。
7、一日うどんツアー
麦畑見学ーうどん学校(うどん作り体験)ーうどん製造工場見学ーうどんマップでうどん屋さんめぐりーうどん歴史博物館見学
8、うどん横丁、うどん館
札幌のラーメン横丁、横浜のラーメン館のようなもの
これは近くに集客力のある施設がだきないと、単独では難しい
先日も、桐生うどん会と麺類商組合青年部の共催でこどもうどん教室を桐生西公民館でおこないました。
麺類商組合、麺類商組合青年部、桐生うどん会でスクラム組んで進んでいけたら10年後には
「西の讃岐に 東の桐生」と言われるようにできると確信してます。
常々、あたたかいご支援ありがとうございます、挫折しそうになつた時もありましたが皆様のおささえで、つづけられております今後ともよろしくお願い申しあげます。