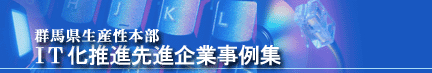
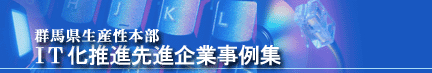 |
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
| ■「コンピュータは 完全に業務に組み込まれている」 (株)カネトモは、カーテンを中心とするインテリアグッズから婦人用衣料品まで繊維製品製造に携わっている。自ら「2.5次産業メーカー」というように、主に受注型の業務形態であるが、提案型の商品開発にも力を入れている現状にある。 同社が、業務活用のためにコンピュータ導入をしたのは1980年代初頭のこと。当時にあっては、大型の汎用コンピュータが主流であったことから、電算室を設け、基幹業務の計算処理を担うものだった。 しかし1980年代以降、急速に進んだ、コンピュータのダウンサイジングと集中管理から分散管理への潮流をいち早くキャッチ。 大型のコンピュータシステムからの脱却を1980年代後半には図っている。 数多くの製品アイテムはもちろんのことだが、その製品納品スパンは、受注からほぼ1週間と短く、それだけに「われわれの仕事の相当部分はコンピュータを使っていかないと不可能。 その意味でコンピュータは完全に業務に組み込まれている」現状と見ている。 ■汎用コンピュータからパソコンへの転換 先にも触れたように同社は汎用コンピュータからパソコンへと転換を図ってきた経緯があるが、そこには、徹底した現場主義が貫かれている。 導入当初からのコンピュータの業務活用を担当してきた富田勝管理本部長によれば「従来の大量生産大量消費の時代と異なり市場の多様化によって、現在取引先からは生地・サイズ・色等まで非常にきめ細かいものが要請されます。それら個別業務の情報の総量は、莫大なものになります。ところが、製造現場でそうした個別的な情報を必要とするのは、担当する二人ないし三人ということになります。このことは、情報の一元管理の問題を示しているんだと思います」と語る。 確かに、莫大な情報の入力業務を考えただけでもその労力・機器導入のコストは大きなものにならざるを得ない。 かといって軽減のために最大公約数的な情報では、実際の現場では、役に立たない。 もちろん市場の多様化、短納期化に対応できない。「ですから最終現場での情報が最も大切であり、必要があればそのデータから汲み上げていけばいいこと」と語る。 さらに「集中管理システムはともすると自動販売機のようにブラックボックス化してしまう。つまりコインを入れると結果がポンと出てくるような。ところが日々の変化が激しいわれわれの業界にあっては、ブラックボックスでは機動力がどうしても落ちてしまう。例えば一つの業務がABCDEの5段階に分かれているとして、Dの部分だけ別な対応が迫られた場合、ブラックボックスになっていると、本来ならDの部分だけ変更すればいいものを、全部に対して処理せざるを得なくなる。これではコスト・時間とも顧客ニーズに応えられなくなる」と。 ■指図書はプリントアウト、 フロッピーが情報媒体、HD使用は慎重 「ITも結局、業務に精通している人間がコンピュータをいかに業務に活用することができるかということに尽きる」と語る。こうした考え方のもと、同社のシステムは自社開発だ。標準化されたフォーマットに細かい情報まで入力された受注データは、各担当者によってフロッピー単位で管理され、現場には、必要に応じて整理した指図書をプリントアウトして回す。ハードディスクの大容量化が激しい昨今だが、「ハードディスクにデータを入れてしまうと、コンピュータが個人専用化してしまう」とあえてハードディスクの使用には慎重。 ■きめ細かい情報が、市場動向を反映する きめ細かい情報の集積は、例えば材質、色といった従来の大型汎用システムでは捉えきれず、また販社などカネトモの各顧客さえも把握しきれない市場の微妙な動きを知る手立てとなるという。「今後、こうした情報をどう業務展開に反映していくかが課題」と富田本部長。ネットワークやコンピュータ使用による業務の翻弄が指摘されて久しいが、現場に根ざした確固とした同社の姿勢には学ぶべきところが多い。 |
|
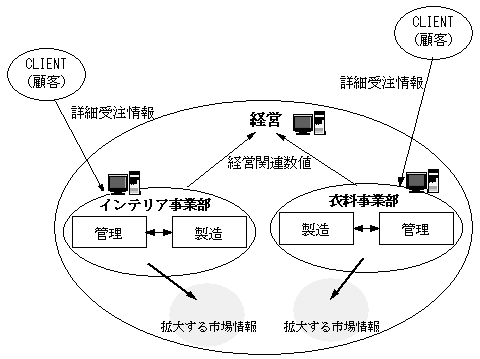 |